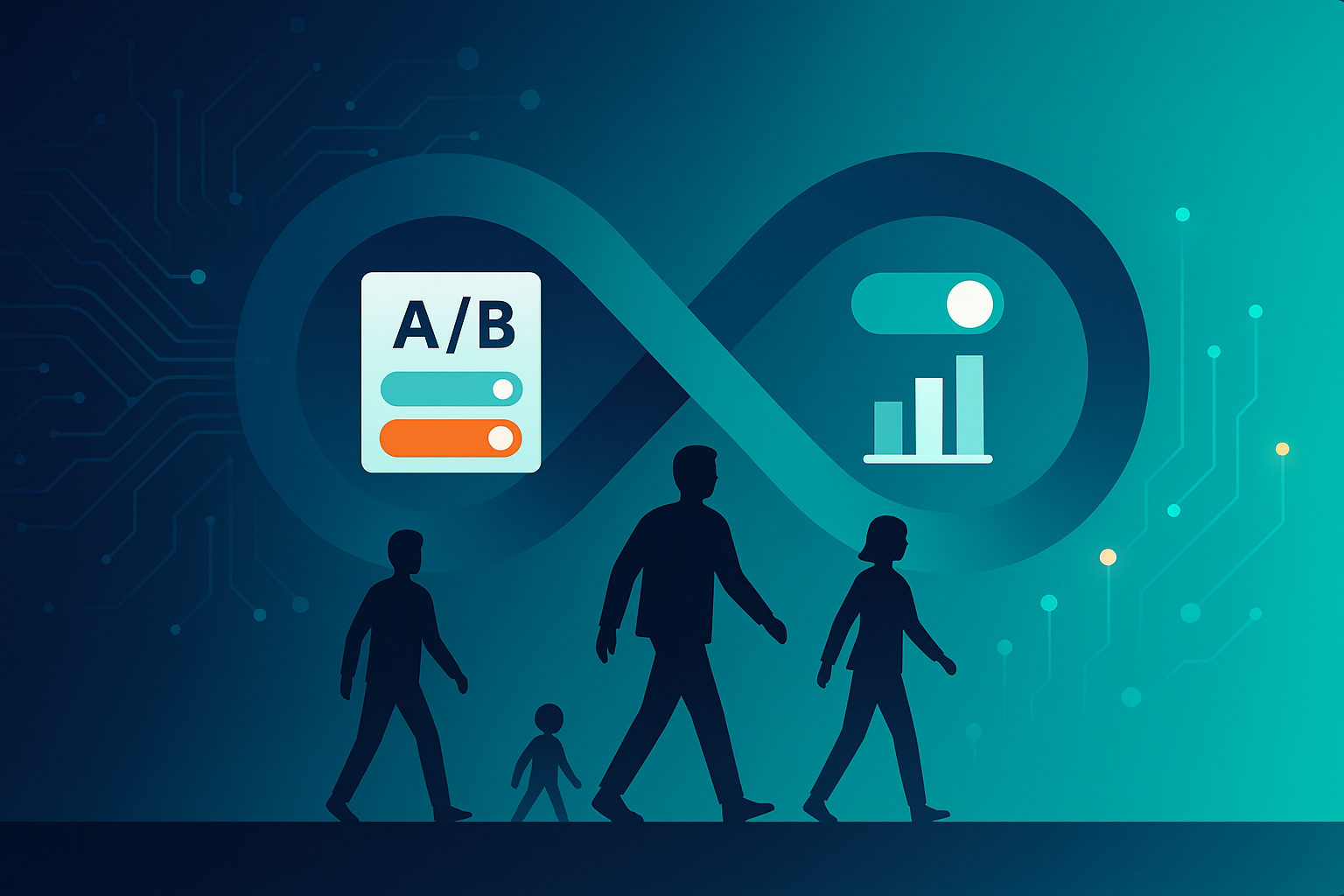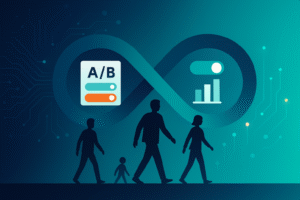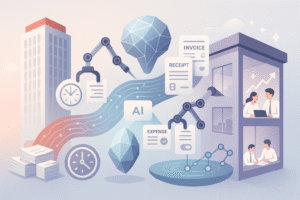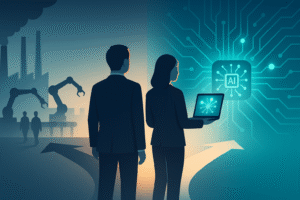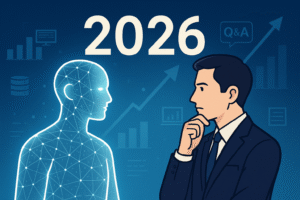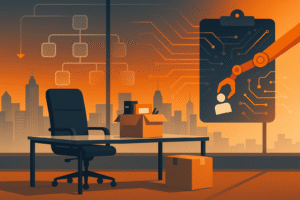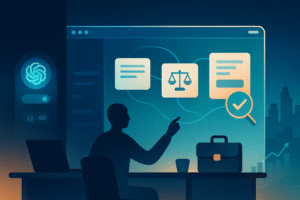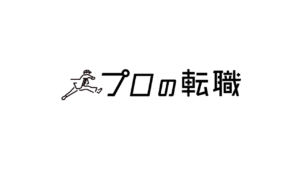OpenAIがソフトウェア分析の新興企業Statsig(スタットシグ)を約1,600億円(11億ドル)で買収しました。単なるM&Aにとどまらず、AIを「製品として成果につなげる力」を取り込む動きです。採用の目線はどこへ移り、転職希望者は何を磨けばよいのか。要点を整理します。
1.買収のポイント:狙いは「実験・検証を回す力」
- 発表時期:2025年9月
- 買収額:11億ドル(約1,600億円)
- スキーム:全株式交換
- 人事:Statsigの創業者ヴィジャイ・ラジ氏はOpenAIのアプリケーション部門CTOに就任予定と報じられています。
OpenAIはChatGPTをはじめアプリケーション領域の強化を進めており、製品実験・機能評価を高速で回す基盤を自社に取り込む狙いが見て取れます。
2.Statsigとは何か:開発者の手元で動く実験基盤
Statsigは2021年創業、シアトル拠点のスタートアップです。A/BテストやFeature Flag(機能の出し分け)をエンジニアがコードレベルで設計・運用できる点が強みです。
従来はマーケ寄りツールに頼りがちだった実験を、開発プロセスに組み込めるため、スピードと精度を両立しやすくなります。Notion、Microsoft、Atlassianなどでの活用が知られ、ユニコーンとして評価額も高まっていました。
3.なぜ今か:AI“単体性能”から“使える製品”へ
OpenAIは2025年に入り、企業価値3,000億ドル規模と報じられるなかで攻めのM&Aを継続。7月にはJony Ive氏率いるAIデバイス企業の買収にも動くなど、ソフト×ハードの両面で「体験」を磨く路線を鮮明にしています。
今回の買収は、「賢いモデル」だけでは差別化しにくい局面で、実験→検証→改善のループを速く回す能力を競争軸に据える動きといえます。
4.転職市場への示唆:評価されるスキルが変わる
これからは、エンジニアやPMに限らずあらゆる職種で「AIを活かして成果を出す力」が評価されます。モデル開発そのものよりも、仮説を立てて検証し、意思決定に結びつける運用力が問われます。
5.「プロの転職」の活用法
業界特化の支援を使うと、学習と市場接続を同時に進めやすくなります。
- 非公開求人の提示:実験・検証を回せる人材を求めるポジションを紹介
- 職務経歴書の磨き込み:成果が伝わる実験設計・評価の記述にチューニング
- 戦略的推薦:スキルマッチの高い企業へ効果的に打診
- 面接対策・タイミング設計:案件の質と数が最大化する局面を見極め
まとめ:次の一手は「実験を武器にする」
OpenAIによるStatsig買収は、実験・検証の運用力がAI開発の中核へ移るシグナルです。転職を考えるなら、A/BテストやFeature Flag、統計的意思決定といった“周辺に見えて中核”のスキルに投資するのが近道です。
最前線で価値を出す鍵は、技術力 × 応用力 × 情報感度。いまの実務を「実験で速く学ぶ」土台に変え、機会が広がるマーケットを取りにいきましょう。