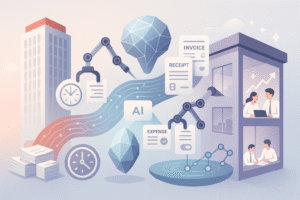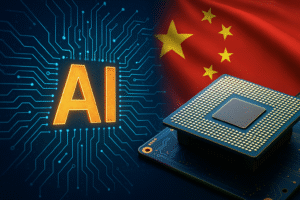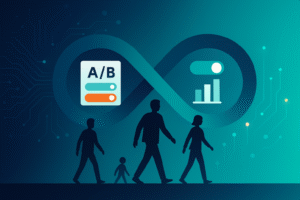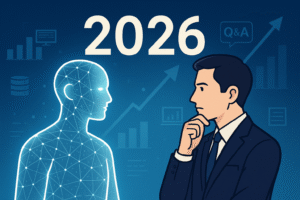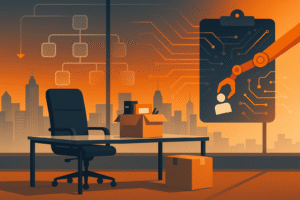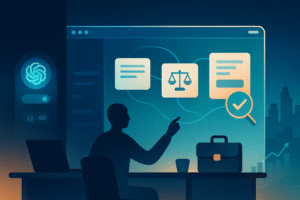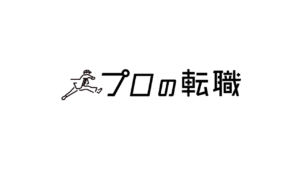金融の現場でDXが加速するなか、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)がスタートアップのLayerXに出資し、同社のAI SaaS「バクラク」や生成AI基盤を取り込む取り組みを進めています。狙いは、単なるコスト削減にとどまらず、ホワイトカラー業務の質そのものを引き上げることです。本稿では、その戦略の中身と、キャリアの観点での示唆を読み解きます。
なぜ今「金融×AIスタートアップ」なのか
金融機関は長らく慎重な変革姿勢と見られてきましたが、近年はAIやSaaSを梃子(てこ)に外部と組む動きが主流になりつつあります。MUFGは「日本全体の生産性向上」を意識し、法人の支出管理やバックオフィスの高度化を重点テーマに据えています。
そのパートナーがLayerXです。2023年6月、MUFGのCVC(三菱UFJイノベーション・パートナーズ)がLayerXへ出資。従来の“請求書が来てから処理する”受動型の業務を、金融機関が能動的に改善提案まで踏み込むモデルへ転換する狙いがあります。スピードと柔軟性をもつスタートアップと組む意義はここにあります。
「バクラク for MUFG」の実像
LayerXの「バクラク」は、請求書処理、経費精算、電子帳簿保存、法人カードまでを横断的につなぐSaaSです。帳票の読取や仕訳、システム連携をAIで自動化し、手作業を大幅に圧縮します。
MUFGは2024年4月にLayerXと業務提携を結び、MUFG向けに最適化した「バクラク for MUFG」を提供開始しました。銀行口座や法人決済との連携により、単なるツール導入に留まらない業務設計の見直しが可能になります。
“仕組み+文化”で進める現場浸透
協業はシステム連携だけではありません。LayerXの社員がMUFGに出向し、行内勉強会などで現場の理解と運用を底上げしています。トップダウンでの一斉導入ではなく、現場と共に作るボトムアップ型DXを志向している点が、定着度合いを左右する重要な設計です。
生成AI「Ai Workforce」で提案力を拡張
2024年後半、LayerXは生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」の本格展開に踏み出しました。MUFGの採用により、提案資料・業務文書の自動作成、要約、ナレッジ共有などが進みます。
とりわけ、過去の提案書を横断検索・再利用できる「データレイク」構想は、属人化を抑えつつ組織知を資産化する要であり、顧客接点での提案の質を底上げします。AIと人が協働するワークスタイルが、金融業界でも標準化する可能性があります。
「年20万時間削減」の中身を解像度高く見る
報道ベースでは、MUFGグループ全体でAIやSaaSの導入により年間20万時間超の削減が見込まれるとされています。重要なのは、「何を減らすか」だけでなく「空いた時間を何に振り向けるか」です。
従来、資料作成や帳票整理といった非戦略業務に偏りがちな時間を、顧客提案、企画、組織改善といった価値創出に再配分する――この“時間のポートフォリオ転換”こそが本丸です。
転職市場への示唆:「AIと働く力」が評価軸に
今回の動きは、キャリア選択にも具体的な示唆を与えます。
- AIと協働して成果を出す人:ツールの使い手にとどまらず、業務設計を含めて結果に結びつける力が問われます。
- 目的から業務を組み立て直せる人:作業のための作業を見直し、KPIや顧客価値から逆算してプロセスを再設計できるかが鍵です。
- 無駄を削り学習を回せる人:省力化で捻出した時間を継続的な実験・改善に投資できる人材は希少です。
こうした素養を持つ方にとって、変化を恐れず「テクノロジー×現場」で成果設計をするMUFGやLayerXのような企業は、魅力的な選択肢になり得ます。
ポイント
- 受動処理から能動提案へ:金融×SaaSの協業は、業務効率だけでなくビジネスモデルの質を変えます。
- “仕組み+文化”の両輪:現場浸透のために出向や勉強会を組み込み、ボトムアップで定着を図ります。
- 時間の再配分が勝負:削減時間を価値創出へ振り向ける設計ができる組織と人が伸びます。
まとめ
MUFGとLayerXの協業は、SaaS導入の範囲を超え、組織の時間配分と知の循環を作り替える試みです。
年20万時間という規模の効率化は、働く個人にとっても「意味のある時間」を増やすチャンスになります。AIと人が補完し合う前提で、自らの仕事の重心をどこに置くか――いま、その再設計が問われています。