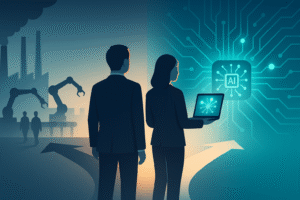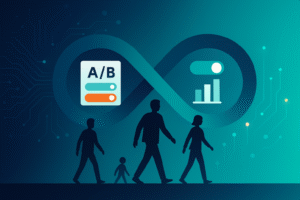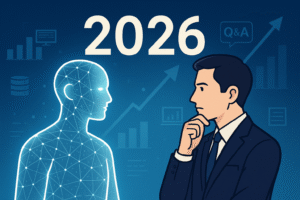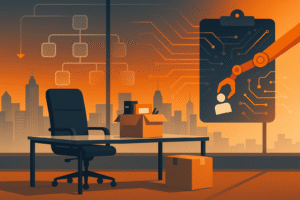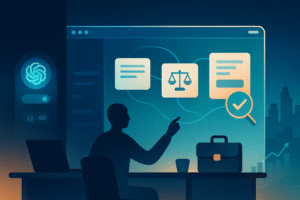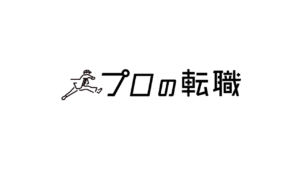2025年上半期、日本の上場企業で「早期・希望退職」の募集が大幅に増えています。対象は黒字企業や管理職層にも広がり、AI活用の加速と産業構造の転換により、「若手だから安心」とは言い切れない局面です。本稿では動向を整理し、備えとして何をすべきかを示します。
何が起きているのか:社数は減、人数は増――1社あたりが大型化
東京商工リサーチによると、2025年1〜5月15日に早期・希望退職を募集した上場企業は19社(前年同期27社)と社数は減少した一方、募集人数は8,711人で前年同期の4,654人から87.1%増と急拡大しました。結果として、1社あたりの募集規模が明確に大型化しています。
象徴例として、パナソニックホールディングスは国内5,000人・グローバル1万人規模、日産自動車はグローバルで約2万人の削減を公表。ジャパンディスプレイは国内従業員の約56%に当たる1,500人を対象としました。いずれも黒字企業であり、「業績が良ければ人員削減はない」という常識が崩れています。
偏在する業種:製造業、特に電機に集中
募集社の多くが製造業で、なかでも電気機器が人数・社数ともに突出。グローバル競争やAI・DX投資の本格化が、人材ポートフォリオ再設計を押し進めています。
黒字でも実施、管理職も安泰ではない
資本効率や成長投資余力を確保する「先手の構造改革」が広がり、役職や年齢に関係なく付加価値で評価する前提へシフトしています。管理職も例外ではありません。
若手への影響:定型業務はAIが代替
資料作成・調査・定型分析といった業務はAIで置き換えやすく、キャリア初期の「数をこなして習得する」機会は縮小しかねません。若手であっても「AIを使い、成果につなげる力」が採用・評価の決め手になります。
下期以降の見通し:2009年ピーク超えも視野
このペースが続けば、2009年(2万2,950人)のピークを上回る可能性があります。米国の関税措置や為替の振れは製造業の収益を圧迫しうるため、工場再編・海外移転とともに人員再配置が進む余地があります。
制度の活用と「自分で動く」
再就職支援やリスキリングの社内外制度は積極的に活用しましょう。ただし、最終的にキャリアを守るのは自分自身の行動です。環境が変わる前から情報収集とスキル形成を進めることが、将来の安心につながります。
まとめ
2025年上半期の早期退職急増は、黒字企業・管理職・若手を問わず広く影響する現実を浮き彫りにしました。AIが定型業務を置き換える時代に「代替されにくい力」を磨くことが最善策です。まずは自分の市場価値を客観視することから。転職エージェント「プロの転職」に登録すれば、専門アドバイザーがキャリア設計を伴走し、変化に備えた行動計画づくりを支援してくれます。今日から一歩、踏み出してみませんか。