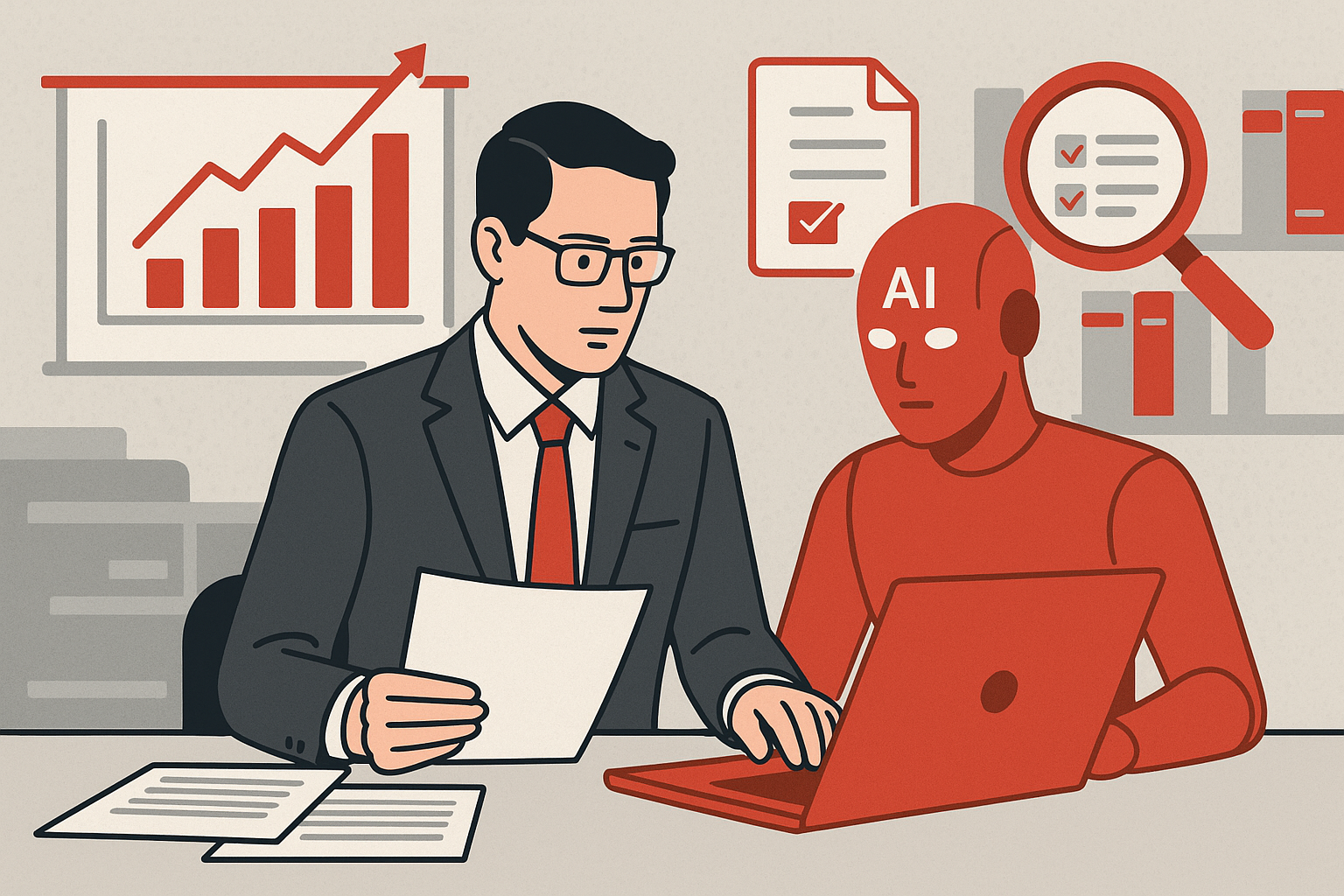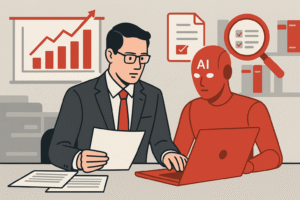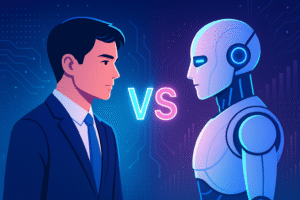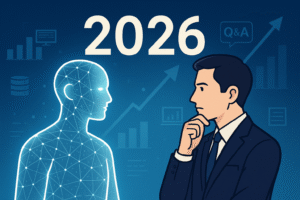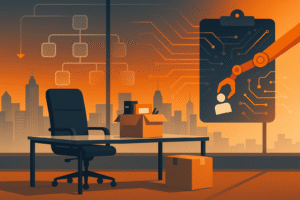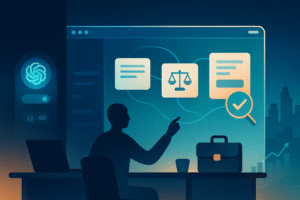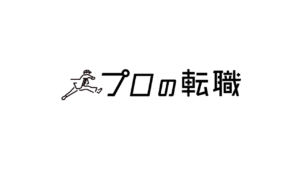生成AIの導入で、PwCジャパンの監査・内部統制の現場が一変しています。作業時間の大幅削減にとどまらず、若手が早期に“判断”と“価値創出”へ踏み出せる環境が整いつつあります。本稿では、その実像と転職で生かす勘所を解説します。
1. 監査の現場で何が起きているのか──生成AIが変えた「一次評価」と準備工程
PwC Japan監査法人は2025年7月、J-SOX(内部統制)関連で生成AIを用いた一次評価の自動化を実証し、「数百〜数千時間」に及ぶ工数削減効果を確認しました。これを基盤に、現場の業務プロセスを診断・再設計する「効率化診断サービス」も始動しています。ポイントは、単なるツール導入ではなく、データフローと権限管理、レビュー規程まで含めて設計された“システム×ガバナンス”の一体運用にあります。
同時に、監査準備の時間は30〜40%短縮。過去の監査調書や業務記述書、統制設計の文脈をAIが高速で読み込み、サマリ化・照合・差分抽出を自動で回すことで、リスク評価やテスト計画立案の初動が桁違いに速くなりました。まさに“熟練監査アシスタント”が常駐する感覚で、担当者は判断を要する論点やサンプル設計の精緻化に時間を振り向けられるようになっています。
ルーチンをAIへ、判断を人へ──。この役割分担が、品質向上と負荷軽減を同時に成立させる鍵になっています。
2. 効率化の先にある「変革」──成果はなぜ二極化するのか
PwCの2024年春の調査では、生成AIへの関心は高まる一方、成果は企業ごとに二極化が進んでいると指摘されました。共通項は二つです。
- ユースケースの設計力:どの工程で、どの品質基準を満たす出力が得られれば価値になるのかを、業務要件から“逆算”して決める力。
- 経営の関与:モデル利用方針、データ管理、責任範囲、教育投資まで一気通貫で後押しする意思決定。
さらに2025年春の世界比較では、日本企業は導入の「推進度」こそ平均的であるものの、「期待を上回る効果」を出した企業の比率は米英に見劣りするという結果でした。単発の自動化で終わらせず、ガバナンス・人材・評価指標を含めた組織設計に踏み込めるかどうかが、成果格差を決めています。PwCジャパンの事例は、この“組織横断の設計力”が効果を引き出す実例だといえます。
3. 若手のキャリアはどう変わるのか──「下積みの意味」がアップデート
生成AIの浸透は、若手の学習曲線を根本から書き換えます。
- 下積みの短縮と早期の判断機会
AIが一次評価や文書処理、過年度比較を担うことで、若手は早期から「リスク仮説の構築」「サンプル設計の妥当性確認」「経営者インタビューの論点出し」など、価値に直結する工程に関与できます。単純作業の量で“経験年数”を積む時代から、判断の密度で成長する時代へ移行します。 - AIリテラシー×批判的思考が“土台スキル”に
生成AIの出力は、正確性・再現性・根拠の説明可能性で評価・補正する姿勢が不可欠です。プロンプト設計や評価指標(Precision/RecallやF1に相当する監査独自の品質メトリクス)、出力ログの保全など、“使いこなし”を証跡と品質で語れる力が問われます。 - 早期専門化とマネジメント素地の並行形成
ルーチンをAIが肩代わりするぶん、データアナリティクス、ITGC(IT全般統制)、サイバー、ESGアシュアランスなど、専門領域の学習時間を確保しやすくなります。加えて、レビュー観点・リスク対話・ガバナンス設計への接点が増えるため、スペシャリストとマネジメントの素地を並行して育成しやすいのが特徴です。
4. 転職希望者の実践アプローチ──“準備の解像度”が差をつくる
生成AIで業務が再設計される中、転職活動で効くのは次の三点です。
- ターゲット選定:AI×業務改革を並走させる企業へ
ツール導入だけでなく、データ管理・レビュー体制・責任分解を設計できている企業は、若手にも早期からコア業務を任せます。PwCの動きはその先行例です。 - スキル戦略:AIリテラシー+業務理解を“証跡化”
「どの工程で、どの品質を、どう担保したか」を説明できるポートフォリオが有効です。
- プロンプト設計と評価手順(再現プロセス)
- 監査メモの自動要約→人手レビューの差分記録
- 統制テストの抽出ロジックと根拠
こうした再現性のある成果物は、面接での説得力を高めます。
- プロンプト設計と評価手順(再現プロセス)
- アクション:情報経路と案件接点を増やす
生成AIの導入が進む監査・リスク・ガバナンス領域の求人は、水面下で動くケースも多いのが実情です。非公開求人へのアクセスを持ち、AI導入度や組織設計の“中身”まで踏み込んで確認できるエージェント経由の動きは有効です。たとえば「プロの転職」に登録し、案件の成熟度(ガバナンス、データ、教育投資)の観点で情報収集と準備を並走させるとよいでしょう。
まとめ
PwCジャパンの生成AI活用は、監査の一次評価や文書レビューを自動化し、品質とスピードを同時に高めています。結果として、若手は早期から判断・検証・戦略立案に関われるようになり、“下積み”の意味が刷新されました。市場全体では成果の二極化が進む中、ガバナンスと人材投資を伴う企業が機会を広げています。将来を見据えるなら、AI×業務改革が進む企業を狙い、実務に根差したAIリテラシーを“証跡”で語れる準備を進めましょう。

参照:日経電子版