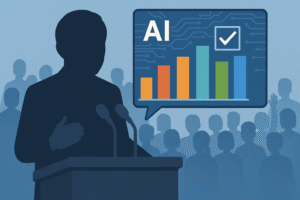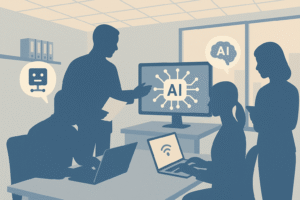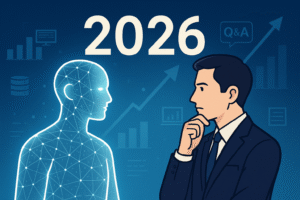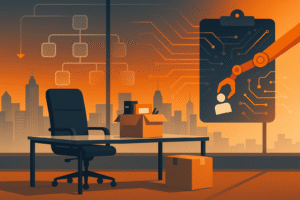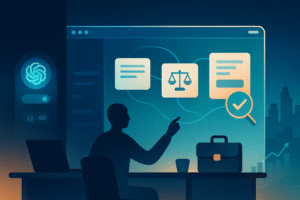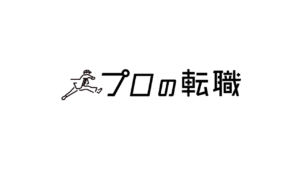人工知能(AI)の進化はビジネスや医療にとどまらず、政治の現場にも急速に波及しています。政党はAIで世論をくみ取り、政策に生かすだけでなく、数万規模の「仮想市民」を生成して社会を丸ごとシミュレーションする試みも始まっています。AIと人間が協働する新しい政策立案の姿が、いま目の前に広がりつつあります。
AIが拾う「声なき声」
従来の世論調査はサンプル数や設問数に限界があり、回答者も偏りがちでした。そこで、SNSや掲示板に投稿された約6万件の意見をAIで解析する「ブロードリスニング」を導入。多様な視点を公約に反映する仕組みを整えました。既存の調査では見えにくかった地域や年代の“声”を政策に取り込んでいます。
仮想市民を用いた社会実験
次のステップは「仮想空間」です。スタンフォード大学とGoogle DeepMindの研究チームは、2時間のインタビューで得た価値観・行動パターンをもとに、1,052人分のAIエージェントを作成しました。エージェントは社会調査の標準であるGeneral Social Survey(GSS)の回答を85%の精度で再現できたといいます。
これにより、政策案を提示して仮想市民の“投票行動”を確認したり、マーケティング施策の受容度を事前に測ったりすることが可能になります。実社会で大規模な実験が難しいテーマでも、バーチャル空間なら迅速かつ安全に検証できるのが強みです。
課題は「信頼」と「倫理」
期待が膨らむ一方で、AIの分析結果に偏りが入り込むリスクは無視できません。データの質が低いと結論もゆがみ、フェイクニュースの影響を拡大させる恐れがあります。さらに、個人情報保護やアルゴリズムの透明性をどう確保するかも大きな課題です。
――それでも、AIを禁止するのではなく、「人間が最終判断を下し、AIの提案を検証する」枠組みを整えれば、リスクを抑えつつ革新を享受できると専門家は指摘します。
AIと政策立案者が“共創”する未来
AIは膨大なデータを一瞬で読み解き、複数シナリオを示すことが得意です。一方、人間は価値判断や倫理的配慮にこそ強みがあります。両者が役割を分担しながら政策を組み立てれば、従来よりも早く、しかも包摂的な施策を打ち出せる可能性があります。
まとめ
AIが生み出す仮想有権者は、政策立案の実験場をバーチャル空間へと拡張しました。政治や社会科学の境界線を越え、企業のマーケティングや自治体のまちづくりにも応用が広がりつつあります。
もはや「AIを使えるかどうか」が、ビジネスパーソンの競争力を左右する時代です。AIリテラシーを高め、自らのキャリア戦略にどう組み込むか――その第一歩を踏み出すか否かで、未来は大きく変わるかもしれません。